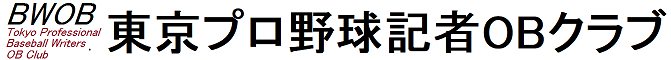「ONの尽瘁(じんすい)」(21)―(玉置 肇=日刊スポーツ)
「あの子は、誤解してる」
「〝あの子〟呼ばわりされる覚えはない!」
1986(昭和61)年、巨人監督・王貞治が投手コーチに招へいした皆川睦雄と先発ローテの一角を占める西本聖は「確執関係」にあった。当時、わたしは「何が不仲の原因か?」「解決の糸口はないか?」などを2人に個別に尋ねた。返ってきた言葉が、冒頭のやりとりである。やりとりといっても、新聞報道を通じての「会話」であり、もはや2人の関係性は、気に障(さわ)るワードに対して感情論で切り返す、不毛の応酬に終始していた。
当時の両者に会話は存在しない。たがいの言い分は新聞報道を通じて知ることになる。反論もまた報道を通じて行われる。言ってみれば新聞が両者の「マッチポンプ」としてお先棒を担いだ、と言えなくもないが、もはや報道を介してしか会話が成り立たないほど両者の関係は冷え切っていたのだ。
ありていに言って、皆川と投手陣の関係はあまりしっくりいっていなかった。抑えの切り札だったサンチェとの衝突に止まらず、西本との折り合いの悪さもチームに暗い影を落とした。
王が、皆川をチームに引っ張ってきた経緯を振り返っておきたい。王政権がスタートした84年から2年間、投手コーチは現役を退いたばかりの堀内恒夫が務めた。選手と年齢も近く「兄貴格」として慕われた堀内だったが、指導経験の浅さは否めず、槙原寛己、斎藤雅樹ら気鋭を「一本立ち」に押し上げるまでには至らなかった。チーム防御率も、84年の3.66、85年の3.96と4点台近くを低迷。不成績の責任をとらされる形で辞任した。新たな投手コーチには投手陣の再整備、大胆な配置転換を断行すべく、情も、しがらみもない「外様」の招へいが模索された。かくして迎えられたのが、皆川だった。
皆川は、女房役の野村克也とは同期入団でともに南海ホークスの黄金期を支えたアンダースローの名手。通算221勝を挙げ、「NPB最後の30勝投手」というレッテルも貼られていた。阪神の1軍投手コーチだった1976(昭51)、77年に山本和行をリーグを代表するリリーフエースに仕立て上げた実績を持つ。現役時から南海とは日本シリーズなどで数々の名勝負を演じてきた王だけに、当時から皆川の人柄は折り込み済みで、加えてコーチとしての適性に目が向いたのも想像に難くない。
皆川にしても、プロ野球界の盟主から声をかけられての〝中央進出〟に力が入らないわけがなかった。ただ、阪神時代のような「功」を急いだ節がないとは言えない。みずからのアドバイスを聞き入れる若手には目をかけるが、ベテランの調整には「我、関せず」を決め込んだ。若手の活躍はもっぱらみずからの功績、とでも言いたげに…。
投手陣の中核だった江川、桑田、斎藤らに対して「スグル」「マスミ」「マサキ」とファーストネームで呼び親しさをアピールするかたわら、先発スタッフとはいえ「一匹狼」だった西本には「あの子」と呼び、気軽に話しかけることもしなかった。
主力選手とコーチとの不和に、王は苦り切った。それでもみずからの介入は控え、当事者間での解決を求めた。事態収拾に乗り出した球団フロントは、皆川が投宿する都内のホテルに西本を呼び寄せ、まず両者を握手させた。さらに投手陣、バッテリー及び担当コーチらによる「和解ゴルフ」を開催。かくして、86年12月、東京郊外のゴルフ場を舞台に両者の手打ちが行われたのだが、V逸という失意の中で執り行われた茶番イベントとあって、とてもこれで一件落着とはならなかった。西本の「首脳陣批判」には球団ワーストの量刑である罰金200万円が科された。
皆川の加入以降に相次いだ投手陣の造反。王政権にとって、チームに及ぼす影響は試合の勝ち負け以上に相当の痛手だったに違いない。それでも王はわずか3厘差で「初優勝」を逃した敗因を、度重なる不祥事に起因させるのではなく、こう言って振り返った。
「まあ、土壇場に来て、広島は強かったですね。でも、それを上回ったとは言わないけど、ウチも同じくらい良い試合をやりましたよ。投げるほうは計算どおり。むしろ、いいくらいだったんじゃないかな。桑田、水野、槙原は3人とも良かった。槙原は実績がある分、『おれは2人とは違うんだ!』という力みもあったけど、途中からはエース並の働きだった」
投手陣の踏ん張りを評価しながら、むしろ皆川の労をねぎらうようでもあった。コーチ、選手の責任は不問に。翻って、全責任は監督であるみずからに在り。それは、退路を断った王らしい総括だった。(続)