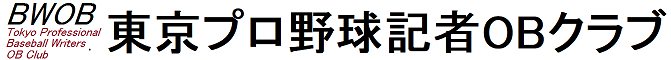「いつか来た記者道」(84)-(露久保 孝一=産経)
◎『若き血』と『紺碧の空』が歴史を作る
昭和100年の懐古調の動きが高まっている。昭和元(1926)年12月25日から1週間後に2年となり、この年、慶大に♪陸の王者ケイオーの『若い血』が誕生した。昭和が始まったころ、野球といえば、プロ球団はなく、東京六大学の人気が高かった。
慶大は学生から、他校を圧倒するような意気上がる応援歌をつくってほしいという要望を聞き、米国帰りの有能な音楽家の堀内敬三に作詩作曲を依頼した。堀内は、「歌い始めの文句は元気のよいものにしたい」と考え、♪若き血に燃ゆる者…とした。この曲を藤山一郎が学生に歌唱指導をする。のちに大物歌手となる藤山は当時、慶應義塾普通部の学生だった。この歌は慶大の選手を勇気づけた。同年秋のリーグ戦で神宮で実演すると、早大に連勝した。
▽応援歌に「敵を倒せ」まで挿入
これにショックを受けた早大応援部は、「負けたのは、慶應の応援歌のせいだ」と叫んだ。そこで、『若き血』に勝る応援歌をつくろうと応援部は歌詞を学内募集し、3年生の詩を選んで名作曲家の古関裕而に頼んだ。6年に『紺碧の空』ができると、早大は活気づき野球が強くなる。『紺碧の空』から15年後、慶大はこの古関に頼み込み『我ぞ覇者』をつくってもらった。歌詞に「早稲田を倒せ」を挿入すれば、翌年早大は再び古関に『ひかる青雲』を作曲してもらい、歌詞に「慶應倒し…」との文句を入れた。「永遠のライバル」の相乗効果で東京六大学の人気と価値を高めていった。
『若き血』をつくった堀内は、7年に『満洲行進曲』を作曲する。同年、古関も『満州征旅の歌』を作曲し、満州ブームをつくった。古関はさらに♪若い血潮の予科練…の『若鷲の歌』などを大ヒットさせる。堀内は、戦時下の曲は一般の男女に向かってつくった国民歌であると述べている。元気づける歌だったのだ。学生野球は、応援歌に支えられて、敵(相手)と激しくぶつかりあい、戦いのあとは健闘を称え合う。戦争とは違い、野球も応援歌も敵と友情的に対決するのは、美しきスポーツ魂の根源である。(続)