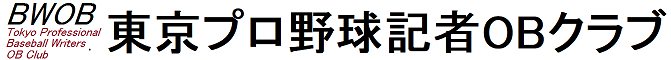◎変化球多投、球審の受難時代(菅谷 齊=共同通信)
試合を実況中継するアナウンサーは1球ごとに球種を教えてくれる。専門家ではないからもっとも難しい仕事だろうと推察する。隣に座る解説者がフォローする情景が浮かぶ。
現代の投手は球種が多い。昭和時代とは比べものにならない。球種の大まかな歴史を振り返ってみると…。
戦前は速球にカーブが基本だった。落差の大きいカーブをドロップと呼んだ。プラスしてシュートがあった。
1931年と34年(昭和6、9年)に来日したベーブ・ルースやルー・ゲーリッグら大リーグの打者たちの打撃フォームを見ると、ほとんどが打つポイントが前だった。速球に遅れないスイングで、変化球が少なかったこが分かる。その大リーガーの影響か、戦後日本の打者もそんな打撃が多かった。
セ・パ2リーグになった50年(昭和25年)に巨人の藤本英雄が初の完全試合を達成したとき、スライダーという球種が注目された。横にスッと逃げるように曲がっていく。その後、中日の杉下茂が武器としたフォークボールが登場した。“魔球”と呼ばれた。
それからシンカー、チェンジアップ、カットボールなど。投手の指の長さなどが違うから同じ球種でも個性がある。
そして今、1試合に登板する投手の数が多い。多くの試合を見ると4、5人が登板している。先発-中継ぎ-クローザーと。球数は150球を数えることがほとんどである。
両チームで300球以上をジャッジするのが球審。1人で全イニングの表裏の投球を判定する。両軍計10投手の球種、それも各投手独自の球種を見ての判定は、大仕事としか言いようがない。試合の終盤になると眼がおかしくなるのでは、と思う。勝負どころでの1球がよく問題になるけれども、同情を禁じ得ない。球審の“受難の時代”といっていい。
昭和時代のように1人の投手が完投するのと比べると隔世の感がある。そのうち球審が前半と後半、あるいは序、中、終盤で代わるときがくるかも知れない。(了)