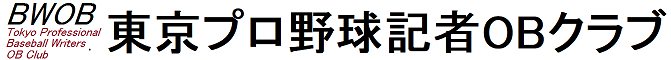◎エクスパンション(菅谷 齊=共同通信)
大リーグは100年以上前から「野球を世界に」との理念を持っている。ベーブ・ルースが1934年(昭和9年)に日本でプレーしたのもそうで、ルースはその後アジアに遠征した。そういった海外遠征はよく行われており、ヨーロッパでも試合を見せた。
野球を国家的スポーツと自負している米国の代表的存在である大リーグは、分かりやすくいえば「100年の計」を持っている。それがエクスパンション(球団拡張政策)である。1901年、ナ・ア2大リーグの近代リーグがスタート。1リーグ8球団ずつの計16チームだった。
当時は東部のチームが多く、セントルイス、シカゴ、ミルウォーキーが東海岸から遠かった。その後、飛行機時代になってドジャースとジャイアンツがニューヨークから西海岸に移動。アスレチックスはフィラデルフィア、カンザスシティを経てカリフォルニアのオークランドにたどり着いた。
62年に2チームずつ増え、各10チームとなった。さらに2球団ずつ増えた69年には1地区5チームの東西制を採用した。94年にはまた2球団が加入したところから中地区を入れて3地区制に。この時は両リーグとも東と中が5球団ずつ、西は4球団という変則だった。現在は両リーグ合わせて30球団。各地区5球団ずつとして戦っている。
地区制を採用したことで地区内対戦が増えたことで遠距離遠征が減った。これで遠征費が激減した。地区とリーグ優勝決定シリーズを増やし、その勝者がワールドシリーズを戦うというポストシーズンを充実させた。このビジネス感覚はさすがである。
それに比べて日本のプロ野球はどうだろう。現在のセ・パ2リーグによる公式戦は50年(昭和25年)から。1年目はセ8、パ7球団だったのが6球団ずつになったのは58年のことだった。その形から変わっていない。変わったのは初期の球団経営で、パは毎日、大映、東急、南海、阪急、近鉄、西鉄すべて消えた。セも松竹、国鉄、大洋、西日本が退き、巨人、中日、阪神、広島が残っている。
ただフランチャイズが札幌と仙台と広がった。しかし、首都東京にパ球団がない。これはビジネス的には課題だろう。
今後、プロ野球の球団は増える可能性があるだろうか。ソフトバンクの王会長が「20球団」と言っている。都道府県に球場はあるのは絶対条件をクリアしている。球団増加でOBの就職(指導者)にとって大きいなどメリットはある。
懸念は、トップクラスの選手が毎年のように大リーグに移る時代だけに、目玉商品のない試合に観客が動員できるか、というビジネスの前提に問題がある。大リーグのような時間をかけたダイナミックな構想を持てるかどうか。